「また泣いてる…どうしていつも、こうなるの?」
スーパーの通路で座り込む子を見下ろしながら、私は思わず目を閉じました。
発達障害のある子どもを育てる中で、限界を感じたことが何度もあります。
正直な話、怒鳴ってしまったことも、私自身泣きながら眠った夜もあります。
この記事では、そんな私が「少しラクになれた」と感じた方法を3つご紹介します。
- 子育てが限界と感じたらやってほしいこと
- 私が限界だと思ったときにやっていたこと
- ADHD当事者でもある私の子ども時代の経験から伝えたいこと
今、限界を感じているあなたのために、心を込めてお届けします。
発達障害児の子育て│限界と感じたらやってほしい3つのこと

発達障害の子供を育てていると、限界だって思ってしまうことってありますよね。
私も、何度も何度もありました。
そんな時、私がやって効果があったなって思うことを3つ、厳選してお伝えいたします
子どものかんしゃく・パニックにどう向き合うか
「もう限界かも…」
私がそう感じた一番の原因は、子どものかんしゃくやパニックでした。
特に外出先で突然感情が爆発してしまうときは、本当にしんどくて。
うちの子は、気持ちが高ぶると壁や床に頭を打ちつけてしまうことがあり
「このまま脳に何かあったらどうしよう…」
と、不安で胸がいっぱいになることもありました。
そんな時、私が少しずつ身につけていったのが「自分なりの対処法を持つこと」。
「こうすれば少し落ち着くかも」という引き出しがあるだけで、気持ちに余裕が生まれるようになっていきました。
私が意識していたこと、3つご紹介しますね。
① まずは、安全の確保を最優先に。
スーパーの通路などで急にジタバタし始めると、商品棚に手が当たって、思わぬケガにつながることもあります。
そんなときは、できるだけ静かで広い場所に、そっと誘導するようにしていました。
② 共感して、落ち着いてから短く伝える。
かんしゃくの真っ最中に、「ダメでしょ!」と叱っても、子どもの耳にはなかなか届きませんよね。
だから私は、まずは「つらいね」「びっくりしたね」と共感することから始めて、落ち着いたタイミングで、短くてわかりやすい言葉で伝えるようにしています。
③ 神経をクールダウンさせる工夫をする。
これは私がとくに意識していたことです。
静かな場所に移動する
たとえばゲームセンターで泣き出したら、少し離れてトイレ近くなど、音の少ない場所へ。
耳からの刺激が減るだけでも、落ち着きやすくなります。
呼吸を整える
深呼吸がうまくできないときもありますが、まずは「ふーっ」と息を吐くだけでもOK。
呼吸が整ってくると、心の嵐もだんだん静まってくるんです。
手を使ってエネルギーの逃がし方を見つける
スクイーズ(やわらかいおもちゃ)をギュッと握らせたり、回転するおもちゃを使ったりするだけで、気持ちがスーッと落ち着く子もいます。
うちの子にはスクイーズが合っていましたが、お子さんによって合う方法は違うので、いくつか試してみると良いかもしれません。
ちなみに、我が家では使いませんでしたが、香りの力を借りている方もいます。
エッセンシャルオイルなど、リラックスできる香りを活用すると落ち着きやすいという声もあるので、気になる方は試してみてもいいかもしれません。
「こうすれば少しラクになるかも」と思える方法をいくつか持っておくだけで、心の余裕ができるようになります。
自分の感情を整えることも、すごく大事
子どものかんしゃくやパニックへの対応はもちろん大事。
でも実は、それ以上に大切だと感じたのが「親である自分の感情の整え方」でした。
私は、息子の状態そのものよりも、周囲からの何気ないひと言に心を乱されることが多かったんです。
たとえば
「支援級なんか行かせないで、親のもとでしつけをすべきじゃない?」
などのアドバイス。
外からの言葉でどんどん心が揺さぶられて、感情が乱れてしまうこと、ありませんか?
そこで私が実践していた、感情を整える3つの方法をご紹介します。
① 少し、物理的に距離を取る
子どもが大暴れして、自分の気持ちまでガタガタになってしまうとき。
私はまず「2メートル離れる」を意識していました。
目の届く範囲にいながらも、少し距離を取るだけで、スーッと心が落ち着くときがあります。
小さな行動から始めていました。
② 感情を紙に書き出して、ビリビリ破く
これは本当におすすめです。
思いっきり汚い言葉でもいいから、心に浮かんだことを紙に全部書き出します。
「最低」
「やってられない」
「なんで私ばっかり」
どんな言葉でもOK。
そして最後はビリビリに破ってゴミ箱にポイッ!
びっくりするくらい気持ちがスッキリします。
③ 感情を数値化して、客観視する
心理学の本で読んで取り入れた方法なのですが、とても効果的でした。
たとえば
「今のイライラは10段階中どのくらい?」
と自分に問いかけてみます。
「今は怒りMAX…8くらいかな」
「少し落ち着いてきた、今は5くらいかも」
そんなふうに、自分の気持ちを数字で表してみるだけで、少し冷静になれます。
頭の中がぐるぐるしているときこそ、『感情を見える化』してあげると、自分を俯瞰できるようになります。
それでも、どうしようもなくしんどいときには…
そんなときは、ためらわずに『外に助けを求める』という選択も必要です。
私自身、電話はしたことがないのですが、「いざという時のために」と思って、
- 児童相談所の番号(189)
- 自治体の相談室の連絡先
を、冷蔵庫の横など目につきやすい場所に貼っていました。
「電話をかけるかどうか」
よりも、
「助けを求めてもいい場所がある」
と思えることが、私にとって大きな支えでした。
「まず自分の心を守る」ことを、後回しにしないでほしいと思っています。
一時預かり、放課後デイも検討してOK
一時預かりや放課後デイサービスの利用を検討しても大丈夫です。
罪悪感を感じる方もいますが、親以外の大人と関わることは、子どもにとっていい刺激になることも……。
発達障害への理解がある施設では、活動を通じて自己肯定感が育まれることも。
情報収集から、気軽にはじめてみてくださいね。
発達障害児の子育て、私も限界と思ったときがありました

発達障害のある子どもとの子育てで、「もう無理かも」と限界を感じたことが私にもありました。
現在、中学2年生の息子は、ASDとADHDの診断を受けており、今は服薬もしています。
特に幼稚園の年中から小学校中学年までは、パニックやかんしゃくが多く、本当に大変な毎日でした。
ときには頭を打ちつけてしまうこともあり
「このままでは命に関わるかもしれない」
と不安でいっぱいでした。
そんな中で私が意識していたのは
「うまくいったことを積み上げていく」
こと。
できたときにはすぐにほめて、不安で手が止まったときには
「前はできたから、大丈夫じゃないかな?」
と声をかける。
小さな成功体験を積み重ねるうちに、少しずつパニックも落ち着いていきました。
中学に入ってからは支援級から普通級に移行し、本人も落ち着いて学校生活を送れるようになっています。
もちろん、服薬や環境の変化も関係していて、「これだけやれば大丈夫」という正解はありません。
でも、「いろんなことを試しながら進んでいくしかない」と気づけたことが、私にとっての救いになりました。
今つらいと感じている方も、どうかひとりで抱え込まず、周りの支援や相談窓口を頼ってくださいね。
お子さんの成長は、きっとこれから見えてきます。
発達障害児だった子供の頃の私から今の私に伝えたいこと

実は私自身もADHDの診断を受けた当事者です。
だからこそ、今、発達障害のお子さんを育てている自分に伝えたいことがあります。
私が子どもだった約40年前は、発達障害への理解はほとんどなく、診断もサポートもありませんでした。
友達ができない、先生は助けてくれない、親からは「もっと頑張れ」と言われる日々。
そんな中で、同じく発達障害だった兄弟は心を病んでしまいました。
私も、感情のコントロールができずに泣いてばかり。
遅刻や忘れ物も多く、「なぜできないの?」と責められることもたくさんありました。
でも皆さんがご存じの通り、行動の背景には『脳の特性』があるんです。
だからこそ、子どもにも「あなたのせいじゃないよ」と伝えてあげたい。
私自身、大人になってから自分の特性に気づき、今では服薬やカウンセリングを受けながら、自分の人生を立て直しています。
自信がなかった性格も、少しずつ変わってきました。
今、目の前の子育てがとても大変だと感じている方も多いと思います。
でも、心も時間をかけて育っていきます。
乗り越えた先には、子どもの成長と同じくらい、親としての成長があります。
私も今、やっとそんな自分と向き合えるようになりました。
一緒に、少しずつでも前に進んでいけたら嬉しいです。
発達障害児の子育てでよく聞く質問
発達障害の診断や服薬にかかる費用が心配です
確かにお薬代が高額になることもありますが、「自立支援医療」などの制度を使えば負担を軽減できる場合があります。
自治体や医療機関に相談してみてくださいね。
夫が理解をしてくれない
私の夫も最初は「頑張ればできるんじゃない?」と理解が乏しく、すれ違いもありました。
でも夫とはぶつからずに、日々の出来事や支援級の先生との面談内容などを、随時報告をし続けました。
夫も自分なりに調べてくれたようで、今では一番の理解者です。
兄弟に時間をかけてあげられない
発達障害のある子の育児中は、兄弟にかける時間が少なくなりがちです。
私も上の子との時間が取れず悩みましたが、下の子が昼寝している間などに、お姉ちゃんとゆっくり話す時間を意識的に作っていました。
外出時に夫と分担して2人で行動することも。
わずかな時間でも「2人だけの時間」を大切にしていました。
大丈夫、子どももあなたも、ちゃんと育っていきます
どんなに嵐のような毎日でも、子どもは少しずつ育ち、あなたも確実に歩んでいます。
自分を責めず、時には頼って、心の余白を持つことも大切です。
あなたとお子さんの未来は、これからきっと明るくなっていきます。

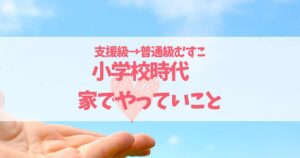

コメント